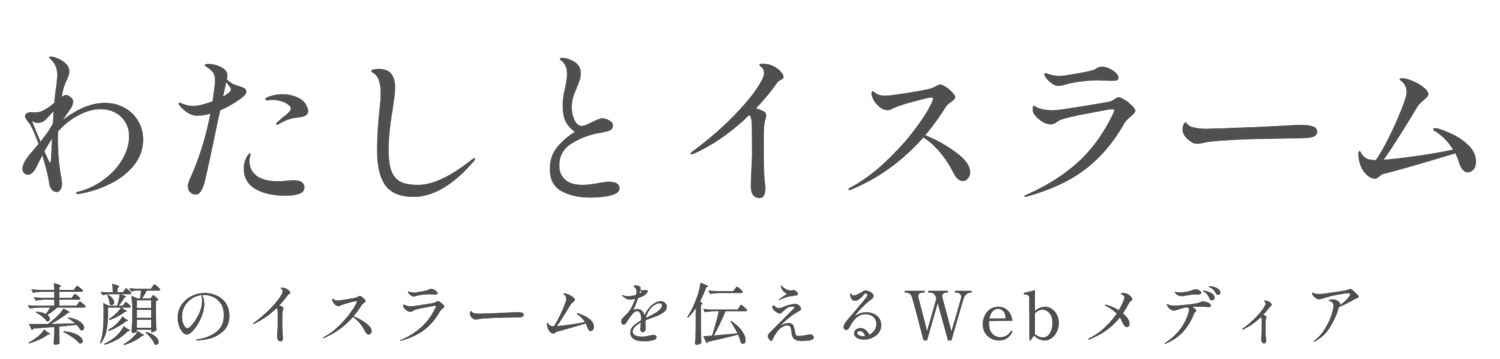辺境のムスリマNanamiの信仰と暮らし:食と場づくりで、本当のイスラームのすがたを伝えたい。
島根の大自然のなかで暮らす一人のムスリマがいます。彼女の名前はNanamiさん。改宗から7年、信仰とともに歩んできた日々は、自然に親しむ暮らしや食の営みへとつながっていきました。
「イスラームは人を優しく導くもの」と語るNanamiさんの言葉には、改宗のきっかけや信仰を続ける中での迷いや支え、そして食と場づくりを通じて人と人をつなごうとする思いが込められています。
── まずは自己紹介をお願いします。
Nanamiと申します。神戸でイスラームに改宗してから7年目になります。モロッコ人の夫と結婚し、島根県に移住して、現在は息子と家族3人で暮らしています。普段は子育て中の主婦ですが、この春からイスラーム圏のお料理を提供する不定期の間借りカフェ「アッサラーム」という活動を始めました。月に一度フランス語講座を開くなど他の活動もしています。
── 島根に移住されたきっかけは何ですか?
結婚したのがちょうどコロナ禍の真っ只中でした。社会の矛盾に強い違和感を覚えたんです。例えば「人と距離を取らなければいけない」と言いながら温泉に行ったり、マスクをつけてお店に入るのに、外して食事をしていたり…。このまま社会に流されていると感覚が狂ってしまうと感じました。
そこで、一度そうした社会から離れたいと思ったのです。当時は夫婦ともにリモートワークができたので、茶道をはじめとする日本の伝統文化や自然が豊かな島根に移り住むことを決めました。
移住の直接的なきっかけである茶道は現在も日々の暮らしの中に。
季節とともに移ろう美しい島根の自然。これは出産直前に見た朝焼け
── イスラームとの出会いを教えてください。
職場や友人関係の中で、周囲にムスリムの方々がいて、彼らが礼拝や断食に真剣に取り組む姿を見たことが大きなきっかけでした。実はそれ以前からイスラームに惹かれる部分があったように思います。
高校時代には世界史の教科書でお祈りの様子を見て真似してみたり、大学生のころフランス留学中に出会った北アフリカなどから来ているムスリム留学生達の人柄に触れて心地よさを感じたり…。思い返せば、幼い頃から国旗の絵を描く授業でサウジアラビアの国旗(シャハーダの文言が書かれている)を選んだりと、不思議とイスラームに惹かれてきたのだと思います。
── 改宗を決意した理由は何だったのでしょうか。
職場のムスリムの同僚のラマダーン断食に興味を持って、翌年興味本位で一ヶ月のラマダーンを経験したおかげで、"食べる"ことの本当の意義を心身の感覚で理解できたことです。「イスラームは人間が正しく生きるために、そっと手を差し伸べてくれる宗教なのだ」と実感しました。
厳しい戒律というより、むしろ人を導いてくれる優しさを感じ、この教えに従って生きていきたいと思い、改宗を決意しました。
── 改宗して最も大きく変わったことは?
「絶対的な基準」を得たことです。情報が氾濫する社会の中で、何を信じたらいいかわからなくなることが多いですが、イスラームに基づいて考えることで冷静に物事を見られるようになりました。
ファッションや食生活に関しても、流行や商業的な情報に振り回されず、「自然なものを大切にする」という軸ができました。お着物を日常的に着るようになったのも風土に合った、自然な素材でできた、そしてイスラームに反さない服装をしたいという考えからですし、お化粧をやめて「他者からこう見られたい」「ここは隠したい」などといった潜在意識を手放して“本来の自分”でいられるようになったのも大きな変化です。
家での食事は和食。地元の旬の素材を、感謝しながらいただく。
普段着はお着物が、日本で過ごすには最適だと感じています。
── 信仰を続ける中で挫折を感じたことはありますか?
一度、「もうイスラームは無理かもしれない」と思った時期がありました。偶然会ったムスリムたちから「女性は外に出てはいけない」「ヒジャーブをかぶらないのは駄目だ」と強く言われてしまうことが続いたんです。
そのときはとても落ち込んで信仰を手放そうとまで思いましたが、たまたま東京出張のついでに友人とブータン料理を食べに行った時に、たまたま時間が余ってひとりで歩いていたら東京ジャーミイが目の前に現れて。せっかくなので中を訪れて初対面のムスリムたちに事情を話してみたところ、「全くそんなことはない!自分のペースで続けていいんだよ」と優しく励ましてもらえました。その経験は、見えない力に導かれているように感じられた、大切な出来事です。
── この春から始められた間借りカフェ「アッサラーム」について教えてください。
もともと料理が好きで、留学時代や海外の友人と交流する中で、いろんな国の料理を作って喜んでもらった経験がありました。また「イスラームってどんな宗教?」と興味を持ってくださる方も多く、もっとオープンに知っていただける場を作りたいと思ったのです。
イスラームの教えを通じて食生活を見直すようになり、ハラールだけでなく、食品添加物や農薬を避けるようになった結果、外食がほとんどできなくなったので自分で作るしかないという状況になったことも大きいです。
そこで、安心して口にできる地元の新鮮な食材と国産のハラルの肉類、トルコ・アフガニスタン・モロッコなど原産地やそれに近いイスラーム圏から仕入れたドライフルーツやスパイスを使い、お料理を提供するカフェを始めました。
── パレスチナとの関わりが大きなきっかけだったそうですね。
はい。パレスチナの状況をただ見ていることしかできないのがつらくて、自分なりに何かできないかと考えました。そこで、間借りカフェを開いて毎回のメニューにパレスチナ料理を一品取り入れ、パレスチナの存在を知っていただき、売り上げの一部を寄付しようと。この思いが、活動を始める決め手になりました。
「自分が働くことで誰かの力になれるかもしれない」という実感が、大きな支え(むしろ救い)になっています。
ある日のカフェメニュー。色んな国の食べ物をを一皿に寄せて。
事実を知るきっかけになればと、毎回設置するパレスチナコーナー。
── カフェでの印象的な出会いはありますか?
普段お世話になっている地元の高齢の方が「どんなものか見てみよう」と訪れてくださったり、ハラールの表示を見て初めて来店したムスリムの方がいたり…。カフェがなければ出会えなかった人たちがたくさんいます。
ムスリムでなくても「イスラームに親しみを持っている」という方が訪れてくださり、「アッサラームアレイクム!」と挨拶して入って来てくださったり、アラビア語が書かれた服を着て来られた方もいて、とても嬉しかったです。
ムスリムとムスリムでない人達の交流もあれば、初対面のお客さま同士がイスラームやアラブ圏の話題でお話に興じているということもあり、イスラームを中心にして食を通じて人と人をつなぐ場になっているなら嬉しいなぁと感じています。
── 食を通じて伝えたいイスラームの魅力は何でしょうか。
イスラームの国々と聞いてもイメージを持っていない人が多いと思います。わたしは「イスラーム圏にはこんなに多様で豊かな食文化がある」ということを伝えたいです。アフリカ、中東、東南アジアなど地域ごとに食材も料理も違いますが、どこでも“その土地の恵み(アッラーからの贈り物)に感謝して食べる”という姿勢は共通しています。
それは日本の食文化とも重なりますし、決して特別に厳しいものではなく、むしろ自然で身近なものだと感じてもらえたら嬉しいです。
── 今後の夢や挑戦を教えてください。
料理教室を開いて、食べ物のことやイスラームのことについてゆっくりお話ししながら、交流できる場を作りたいと思っています。 また、今住んでいる古民家を活用して農家民宿のような宿泊施設を始める構想もあります。そこで一緒に料理や文化体験をしたり、「イスラームに基づいて日本の田舎で生きるというのはこういうことか」と感じていただけるような場にしていきたいです。
さらに「わたしとイスラーム」を通じて、日本社会にイスラームの本当の姿を広めたいと思っています。メディアが伝えるイメージだけでは誤解が残ってしまいますが、実際のムスリムはもっと身近で温かい存在です。その姿を、記事や場づくりを通して多くの人に知ってもらえたらと思います。
編集後記
Nanamiさんの言葉からは、「イスラームの教えに則して自由に自分らしく生きること」と「日本の文化を大切にすること」が矛盾せず、むしろ互いに豊かに響き合っていることが伝わってきました。
食や日々の暮らしを通じて、イスラームの自然さや優しさを広めていくNanamiさんの活動は、島根の小さな町から大きな波紋を広げていきそうです。
(2025.8.28 / 聞き手・編集 Yuki)
【語り手プロフィール】
Nanami
出雲國の辺境の地に夫と子1人の3人で暮らす改宗ムスリマ。お隣さんとお茶を飲みつつ話すくらいの気軽さで皆がイスラームに親しめる機会というものを常々望んでおり、「わたしとイスラーム」がそんな場所になればよいなと願っています。大好きな出雲國では、地域の人々に食を通じてイスラームに親しんで貰いたい想いで、不定期でイスラーム圏のお料理を提供する間借りカフェ アッサラームを開催。